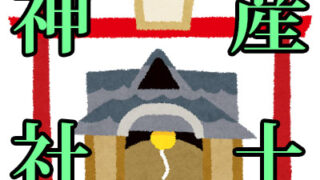
産土神社が分からないからといって鑑定してもらう必要はあるのか?
人に鑑定してもらってまで産土神社を知る必要はあるのでしょうか。
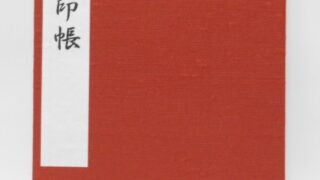
御朱印の迷惑トラブルから御朱印の有り様を考える
近年は御朱印ブーム。神社に御朱印を受けに来る人が増えて、大きな神社だと御朱印待ちの人で列が ...

時代劇で神社のお札が玄関の上に内側を向けて貼られているのはなぜか?
自分は時代劇をちょくちょくみるのですが、町民の長屋とかのシーンで玄関の人が出入りするところ ...
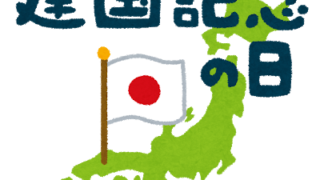
建国記念日と紀元節と皇室と
さて先日2月11日は建国記念の日だったわけですが、建国記念の日って何を記念した日か知ってい ...

伊勢神宮はなぜ世界遺産じゃないの?それは式年遷宮があるから!
伊勢神宮といえばみなさんも聞いたことがある有名な神社ですよね。 正式名称は「神宮」だったり ...

悪い神様を祀っている神社がある?
みなさんは神社の神様に対してどんなイメージを思い浮かべますか? 「いつも見守ってくれてる」 ...

神社と賽銭泥棒・室外機を盗むやつらも・・・
神社に設置されている賽銭箱。ここにお賽銭が入っているのは皆さんご存知のことかと思いますが、 ...

祭りという言葉の語源・どんな意味がある?
「祭り」というと皆さんどんなことを思い浮かべるでしょうか? 「お神輿をかついでワッショイワ ...
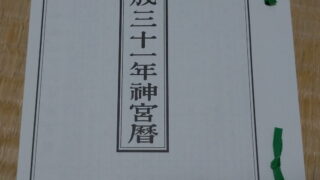
神宮暦を買ってみたよ!読み方・どこで買える?価格など!
今日は神宮暦についてちょっと書いてみたいと思います。 「神宮暦ってなんじゃらほい?」って思 ...