祭りという言葉の語源・どんな意味がある?
「祭り」というと皆さんどんなことを思い浮かべるでしょうか?
「お神輿をかついでワッショイワッショイ!」
「露店が出て賑やかにドンチャン騒ぎ!」
とかそういうことを思い浮かべる人が多いと思います。
でも神主の感覚からすると「祭り」ってそれだけじゃないんですよね。そんなわけで今回は祭りという言葉について考えてみたいと思います。
神社関係で祭とつくものについて考えてみる
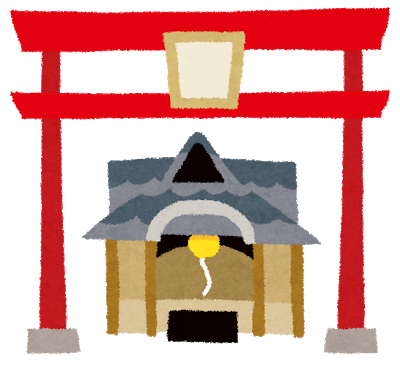
神社関連で祭が付くものについて思いついたものをざっと挙げてみます。
- 日供祭(にっくさい) 国や地域、氏子さんの発展を願い毎日行う
- 神葬祭(しんそうさい) 神主がやるお葬式(神社では行わない)
- 焼納祭(しょうのうさい) 正月飾りとか御札をお焚き上げするときにやるやつ
- 地鎮祭(じちんさい) 家を建てる前に神様に報告するやつ
とかいろいろです。
こうやって見るとお葬式にも「祭」と付いていて、何もワイワイ騒ぐだけが祭りではないということがわかりますよね?
神主の感覚としては、神様に関する儀式を行うことが「祭」っていう感じです。
お神輿をワッショイワッショイ担いだり、芸能を披露したりして賑やかにするのも確かに「祭」なんですけど、それはあくまでも1つの側面であって、賑やかでない祭りもあるんですね。
ちなみに神様の前で歌や踊りなど芸能を披露することを神賑(しんしん)行事といいます。神様の前で芸事をすることで神様の力が高まり、その力を再び人間にももらおうって趣旨だと思います。たぶん。
ワッショイの意味
 (イラストは適当に持ってきたので深く考えないでください)
(イラストは適当に持ってきたので深く考えないでください)
余談ではありますが御神輿担ぐ時のワッショイワッショイという掛け声の語源は「和を背負う」といところから来ており、皆で神輿を担ぐことで皆に調和をもたらすという意味があるらしいです。
どこかの宮司さんが言ってました。
本当かどうかは知らん!でもまあ確かになるほどなってなる話です。
オイ…また話が逸れたぞ…
祭の語源て何なの?
ワッショイの語源の話が出たところで祭の語源についても書いてみたいと思います。
これも神社で仕事(ほんとは奉仕っていうけど)をしていた時にいろんな人から聞いた話なんで本当かどうかは知らん!ってことなわけですが興味があったら読んでください。
「集まる」から来ている説

神社でのお祭りをするときってだいたい人が集まって行います(日供祭は一人でやることもあるけど)。
お供え物を準備したり、祭の場所を整えたり、いろんな人の力があって祭を行うことができます。
皆が集まるという意味の「まつろう」という言葉があるらしいんですが、この「まつろう」が変化して「祭」になったという説です。
祭って何かの目的のために人が集まってくるからなるほどなって話です。
「待つ」から来ている説

お祭りというか儀式においては関係者皆で準備を万全に整えて式が始まるのを心静かに待ちます。
この「待つ」から来ているという説です。神様のことを行うに際して皆が気持ちを合わせ祈ることができるように静かにして待つ時間って確かに必要なのかもなって思うところではあります。
順う(まつろう)から来ている説
神様に付き従う「順う」という言葉から来ている説もあります。
神事では神様にずっと奉仕しているわけですので確かになと思わせられる部分です。
祭はみんなでやるものさ!

ってなわけで祭の意味とか語源について書いてみたんですけど、常に皆が気持ちを合わせるってことが関係してくるって気付いた人もいるんじゃないでしょうか。
またまた余談です。地鎮祭とか儀式のあとにみんなでお酒を飲んだりする直会(なおらい)ってのがあるんですけど、「直し会わせる」と読むことができて、同じ方向を向いて物事に取り掛かることができるようにという意味があるようです。
話がどんどん逸れていってしまっている気がしますが、いままでのことを箇条書きにしてみると…
- 賑やかにするのは祭の1つの側面
- 祭の語源は「集まる」「待つ」「順う」などの説がある。
- 祭には皆が気持ちを合わせるためのことがたくさん
という感じかな!?
神社の祭りって神様のことをするのはもちろんなんですけど、祭に関わる人たちの調和という意味合いもあると思います。
もし、あなたが神社のお祭りなどに携わることがあったらそうしたことも思いながら参加してみてはどうでしょうか。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません