神無月(10月)は神社にお参りしても神様はいないから意味ないの?

以前神社にいたときに参拝者からこんな質問をされたことがあります。
「神無月(かんなづき)って出雲大社に神様達が集まるから神社に神様はいないの?」
で、この質問をされたときに神無月に神社にお参りしても問題ないということは頭ではわかっていてもなかなか論理的な説明ができなくて悔やんだ記憶があります。
てなわけで今回は神無月、に神社にお参りしても大丈夫な理由を自分なりにまとめてみます。
神無月って何月?参拝しても意味ないというのはなぜ?
神無月は何月かご存じの方も多いと思いますが10月のことです(旧暦で考えると11月頃)。
そしてこの10月に神社参拝しても意味がないという話が広まった理由は出雲にあります。
出雲では神無月に神様が集まってくると言われており、そのようないわれから10月のことを神無月ではなくて「神在月(かみありづき)」と呼んでいるそうです。
出雲に神様たちが集まるのでそれ以外の地域では神社は留守になっていてお参りしても意味がないと考える人たちが出てきたというわけです。
神無月でもOKな理由1・神無月の「無」は助詞の「の」である
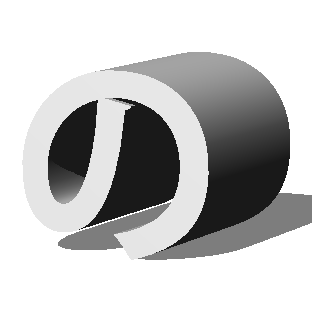
秋のシーズンは多くの作物の収穫を感謝するお祭りが各地の神社で行われており、神様のお祭りが非常に多いシーズンです。こうしたことから神の月とも言われています。
こうしたことから「無」は助詞の「の」であり、現在は我々が使っているように物の有無を表す言葉ではないということです。
6月のことを水無月といいますが6月は梅雨のシーズンも重なることから水が無いというイメージはありませんよね。こうしたことから水無月も「水の月」という意味だという説があります。
神無月の語源としてはこの他、神様にその年取れた作物である「新嘗(にいなえ)」を準備する月「神嘗月(かんなめづき)」が変化したという説もあるようです。
神無月でもOKな理由2・同時に違う場所からお参りできる
神無月は神様の月ということで神社にお参りしても大丈夫なんですが、仮に神様たちが出雲に集まっていたとしても大丈夫です。
人間の場合は当然違う場所に同時に存在することはできないのですが、神様の場合は話が別です。
例えば菅原道真公をおまつりした天満宮。○○天満宮というなまえで各地にありますよね。火の神様の秋葉神社もそうですし、有名な鶴岡八幡宮は源頼朝が京都の石清水八幡宮から神様を勧請してお祀りしたのが由緒です。
神様に対して1箇所からしかお参りできないのであれば「これらの神社にお参りしてる意味は・・・」ってなっちゃいますよね。
神様は分霊ということができるんですね。分身して違う場所に同時に存在できるというイメージ。だから仮に神様たちが出雲に集まっていらっしゃったとしても神社にも神様のはいらっしゃるのでお参りして何の問題も無いと思います!
神無月でもOKな理由3・神社は神様を感じるための場所

先ほどの内容ともちょっと重なるところもありますが、神社に神様が居ると考えるのではなく、神社はいろんな場所から神様の存在を感じるための場所であるという考えです。
神社の建物の雰囲気や周囲の自然、天候の変化など神社の中でいろんなことを感じ取り、神様という人間よりもはるかに大きな存在を感じ取るという自分の感性が大切なんじゃないかなと。
個人的には神社は神様を象徴するような御神体がお祀りされていて神様の存在を感じ取る場所(神社の周りの鎮守の森や自然も含めて)なので、神様がいるとかいないとか深く考えず、自分で神様のことをイメージしてお参りできたらいいんじゃないかなと思います。
神社は神無月でも何月でもお参りしても大丈夫だぞ!
てなわけでぐだぐだと書いてしまいましたが、月なんて気にせず自分が神様にお礼を申し上げたいとき、特に用事は無いけど近くを通ったとき、いつでも神社にお参りして大丈夫です!







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません