
地鎮祭の日取り決定の方法・・・土用や三隣亡はだめなの?
家を建てる前に行う祭事である地鎮祭。この日取りにこだわる人ってけっこういるみたいです。 自 ...

現代の地鎮祭事情・氏神様に頼まないと駄目?
家を建てる前に行う地鎮祭。 工事の報告をし、工事の安全をお願いするのが主な目的の神事です。 ...

年末に神社にお参りしたりお札を受けるのはよくないの?
年末に神社にお参りするというと 「1年も終わるのに年末にお参りしても意味ないでしょ」 とか ...

神社のお参りやお祓いに六曜(大安・仏滅)は関係あるの?
神社のお参りや御祈祷に六曜は関係あるのか、六曜の説明も含めて書いてみました。

おみくじの意味と順番 結んで帰るべきか持って帰るべきか
おみくじを引く目的や順番、結ぶべきか結ばないべきか、写真に撮ってもいいかどうか、変わったお ...

お札やお守りはなぜ1年で返さなければならないのか
神社のお札やお守りに関する決まりごとで1年経ったら神社に返してくださいというものがあります ...

お守りやお札は違う神社のものを複数持つと喧嘩する?持ち方は?いつまで持ってていいの?
お守りは複数持っていていいのか、いつまで持っていていいのか、返納するべきなのかといったこと ...

忌中は絶対に神社にお参りをしたり神棚の祀りをしてはいけないの?
身内の人が亡くなってから最大50日間、忌中といって亡くなった人のことを偲んで神棚の祀りや神 ...
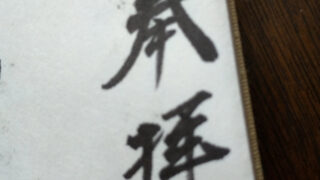
御朱印を書く神主側の3つの気持ち
私もときどき御朱印もらってます 世の中は空前?の御朱印ブーム。 御朱印ガールなんて言葉が登 ...
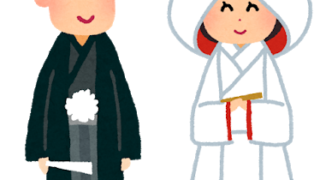
神前結婚式の代わりに結婚奉告祭はどお?費用や流れなど
結婚奉告祭とは何なのかという札名から費用、服装、参列者、流れなど結婚報告祭に関することをま ...