
宮司さん・禰宜さん?神主の呼び方ってどんなのがあるの?
神社にいて祭事を行う人のことみなさんは何て呼んでますか? 神主さん、宮司さん、神官さん・・ ...
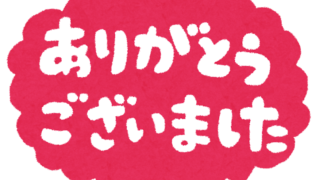
神主は「ありがとうございました」って言わない?
なんだか釣りみたいなタイトルにしてしまいましたが、神主はじめ神社にいる人って客商売にくらべ ...
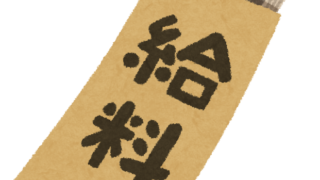
神主の給料はどこから出る?神社本庁との関連は?休みや待遇・続ける理由も
神主の給料・・・金額から出どころまで気になっている人はけっこういると思います。今回はそんな ...

神社で奉仕してみて変わった祝詞への意識・仲執り持ちの意識を持ちたい
神主が神様の前で奏上する祝詞。様々な祈願の内容があり、神様へ願意を伝えるためのものです。 ...

神主が手に持っている木の板は何ていうの?笏(しゃく)です
神主さんが持っている木の板・・・「何のために持っているんだろう?」「何ていうんだろう?」と ...

神主に定年退職はあるのか?引退の時期は?
今回は神主の定年退職について書いてみたいと思います。 神主に定年退職があるのかという話です ...

女の神主がいるって知ってた?女性神職の歴史と現在
灘 伏見さんによる写真ACからの写真 みなさんは神社に居る女性と言うと巫女さんをまっさきに ...

巫女さんってどうやってなるの?年齢制限や結婚事情や仕事内容は?
神社の巫女さんってそのかわいらしい姿から憧れる人もけっこういると思いますが、実際にどんなこ ...
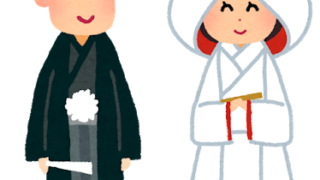
神主の出会いや結婚事情・神社の息子とそうで無い人の違い
普通の人からするとなかなか想像のつかない神主の結婚事情。 興味がある人もけっこういると思い ...
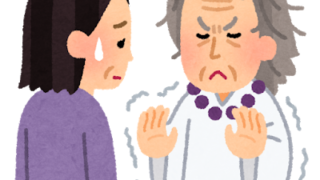
神主って霊が見えるの?霊感はあるの?除霊して欲しいんだけど・・・神主の役割とは
神主の経験があるというと、「霊感があるの?」「霊とか見えるの」と聞かれることがたまにありま ...